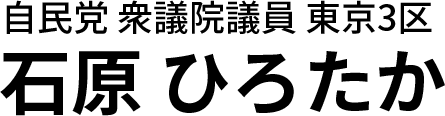○石原委員 自由民主党の石原宏高でございます。
本日は、盗難特定金属製物品の処分の防止に関する法律案について質問をさせていただきたいと思います。
まず最初に、坂井大臣にお伺いしたいと思います。
今回、この法律案が提出された背景には、近年の金属盗の顕著な増加があることは言うまでもありません。その対策には、犯罪者を取り締まるだけでなく、盗品の流通を遮断することで犯罪の発生そのものを抑止する必要があります。
他方、そのために、金属くず買取り業者さん、大多数はきちんと商売を営まれている業者だと思いますが、そんな方々にも新たな負担をお願いすることになります。また、太陽光発電の設置やメンテナンスの業者さん、ひいては正当な目的で必要な工具を所持している方にも影響が及びかねません。そういった点にも配慮が必要だと思います。
そこで、大臣に伺います。
今回の法律案を提出するに至った背景及びその意義、期待される効果についてお答えください。
○坂井国務大臣 昨今、太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗を始めとする金属盗が増加をしております。令和六年の金属盗の被害額は約百四十億円であり、窃盗全体の被害額の二割となっています。
この種の事案が発生した場合、盗難自体の被害にとどまらず、太陽光発電施設であれば電力供給ができないことによる経済的損失も生じたりいたしまして、国民経済に大きな影響が及んでいることから、対策は急務であり、今回、特定金属製物品の窃取の防止に資することを目的とした本法案を提出をさせていただいたところでございます。
また、これら窃盗には、不法滞在外国人グループらによって広域的、組織的に敢行されている実態があり、一部の悪質な買取り業者の存在がこれを助長しているなど、治安上の大きな課題となっております。
現在、十七の道府県において、いわゆる金属くず条例が制定されているところでございますが、この条例が制定されていない都府県の金属くず買受業者に盗品が持ち込まれる事例も多く、先ほど県またぎという言葉もありましたけれども、法律による全国的な規制が必要かと思われます。
本法案の意義等については、金属くず買受業に係る措置により、窃盗犯による盗品の換金が困難になること、犯行用具規制により、特定金属製物品が窃取される前の先制的な対処が可能となること、盗難防止情報の周知により、各事業者が効果的な防犯対策を講じることで、特定金属製物品が盗まれにくくなることが挙げられ、これらによって金属盗が大きく減少することを期待しているものでございます。
○石原委員 大臣、ありがとうございました。
二問目ですけれども、警察庁の実務統計によると、令和六年の金属盗のうち五五・五%が金属ケーブル、材質別では五四・一%が銅であるとされています。そのため、今回の対象金属は、早急な対策が必要な銅が法律上規定をされておりますけれども、今後、対象となる金属を銅以外に広げることはあるのでしょうか。また、その際の基準はどのようなものでしょうか。
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
本法案では、昨今の金属盗の被害状況に鑑み、法の規制対象となる特定金属として、法律で銅を明記しつつ、その他の金属につきましては政令で定めることとしております。当面は銅を対象とすることを考えておりますが、今後、銅以外の金属の盗難被害が増加するなどした場合には、政令で当該金属を特定金属として規定してまいりたいと考えております。
この特定金属を定めるに当たりましては、当該金属を使用して製造された物品に係る窃盗の認知件数及び被害額や、当該金属の取引価格の状況などから、盗難を防止する必要性を総合的に考慮して、特定金属として指定するかどうかを判断していくこととなります。
○石原委員 ありがとうございます。
次に、金属くず買取り業者の現状についてお尋ねをいたします。
全国にどのくらいの数の業者がいるのでしょうか。また、その分布、規模など、分かる範囲でお答えください。
また、現在、買取り業者はどのような顧客から金属くずを買い取っているのでしょうか。お伺いしたいと思います。
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
全国に存在する金属くず買受業者の正確な数は把握できておりませんが、いわゆる金属くず条例が令和五年以前から施行されている十六道府県における営業の許可又は届出の件数の合計につきましては、令和五年末現在で二万二千八百三十四件となっております。この件数などを基にしますと、全国に数万程度の金属くず買受業者が存在しているものと考えております。
また、金属くずの買受けにつきましては、業界団体によりますと、工場から発生する端材などの金属くずにつきましては金属製品メーカーなどから、市中から発生する金属くずにつきましては回収事業者、建築物の解体事業者、車の解体、リサイクル工場、自治体などがその顧客となっているとのことでございます。
○石原委員 ありがとうございます。
実務統計のある太陽光発電施設での金属ケーブル盗難について伺います。
検挙された者のうち外国人の割合はどの程度でしょうか。また、単独犯でしょうか、それともグループ犯でしょうか。グループの場合、どのようなグループなのでしょうか、報道でよく耳にするSNSを通じた仲間集めをしているのでしょうか。また、犯罪を犯した際には、不法滞在だとして、そもそもどのような資格で日本に滞在しているのか、教えてください。
○谷政府参考人 お答えをいたします。
太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗で検挙した外国人についてのお尋ねがございました。
令和六年中における検挙人員は百四十七人となっておりますが、このうち外国人は百十人と、検挙人員全体の約七四・八%を占めております。
次に、これらの被疑者が単独犯かグループ犯か、また犯行グループについてどのようなものかというお尋ねがございました。
こうした太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗は、そのほとんどがグループによって敢行されております。また、御指摘のようなSNS上で不特定多数の者に向けて犯罪実行者を募集して犯行グループを形成するというよりは、むしろ外国人同士の知人関係などを通じて知り合ったメンバーらで犯行グループが形成されていることが多いと見ております。
続きまして、太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗で検挙した外国人の在留資格などについてお尋ねがございました。
令和六年中に検挙した外国人百十人のうち不法滞在は八十九人と、外国人全体の約八〇・九%を占めております。不法滞在の在留資格別の内訳については、技能実習が六十人と最も多く、不法滞在全体の約六七・四%、短期滞在が十七人と次いで多く、不法滞在全体の約一九・一%を占めております。
○石原委員 用意した質問が多いので、飛ばします。
次に、本法律により切断工具、ケーブルカッター等を隠匿携帯することが禁止されますが、隠匿携帯とは具体的にどのような場合でしょうか。ケースに入れた工具を車で運んでいたら該当するのでしょうか。先ほどもちょっとお話もありましたが、手に持って歩いている場合等はどうなるのでしょうか。教えてください。
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
一般的に申しまして、犯罪を企図している者は、犯行を容易にするため、周囲の人間の注意を引かないよう例えば犯行用具を隠して携帯、持ち運びするのが通常であるというふうに考えております。
本法律案の参考としましたいわゆるピッキング防止法におきましても、同様の考えから、人目に触れないように隠して携帯していることの危険性の高さに着目して指定侵入工具の隠匿携帯を禁止しているところでございますが、本法律案におきましても、ケーブルカッターなどの指定金属切断工具につきましては同様の規制を行うこととしたものでございます。
指定金属切断工具の隠匿携帯規制に該当するかどうか、これにつきましては、先ほども申し上げましたとおり、個別具体の事例に基づいて判断することとなります。一義的には、業務その他正当な理由があるか否かということが問題になりますが、その上で、一般論として、隠してということでございますので、他人の目に触れないようにしているということが重要な要素になってこようかと思っております。
他人の目に触れないようにあえてケーブルカッター等をケースに収納して車に積んでいるような場合は隠匿携帯に該当してくる可能性もあるというふうに考えておりますが、ケーブルカッター等を他人の目に触れるような状態で堂々と携帯しているような場合は、これは隠匿携帯には該当しないものと考えております。
なお、電気工事等に従事する方が業務のためにケーブルカッター等を携帯するような、業務その他正当な理由によって携帯する場合は本規制の対象にはなってはおりませんので、このことにつきましては、関係する業界団体等を通じまして御説明してきたところであり、引き続き丁寧な周知に努めたいと考えております。
○石原委員 この点は、是非丁寧な周知をお願いしたいと思います。
昨今、外国人による組織犯罪が増加していますけれども、SNSで仲間を募って犯罪を繰り返す例も報道等でよく耳にします。今回の金属盗についてはそのような例は少なく、外国人などのコミュニティーなどで仲間を集めて犯罪に参加をしているという説明がありましたけれども、そうすると、そのような外国人コミュニティーに対して犯罪防止の取組を、いろいろと事前に説明をして、させないような努力というのが必要だと思うんですけれども、警察庁、警察で外国人コミュニティーに対して犯罪に加担しないようにどのような取組をされているのか、教えてください。
○谷政府参考人 警察におきましては、在留外国人が多く集住する地域、在留外国人が多く所属する企業や学校といった外国人コミュニティーについて、犯罪組織の浸透の防止などのため、関係行政機関や企業等と協調いたしまして、防犯についての広報啓発活動や通訳人との連携等による巡回連絡、コミュニティーの実情に応じた施策を適切に行うための実態把握の推進、違法行為に対する厳正な取締りなどの取組を実施しているところでございます。
引き続き、各種警察活動を的確に行い、外国人コミュニティーへ犯罪組織が浸透することのないよう取り組んでまいりたいと思います。
○石原委員 残り三分ぐらいになりましたので、最後の質問にしたいと思います。
古物営業法において、一万円以下の取引については本人確認が不要とされています。他方、本法律案では、そのような免除規定は置かれていません。もちろん、銅線なんかを大量に持ち込んで一万円ということにはならないと思うんですが、その理由についてお聞かせください。
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
古物営業法におきまして、対価の総額が一万円未満である取引をする場合、取引の相手方の氏名等の確認義務を免除しておりますが、これは、古物商の負担軽減を図るために導入されたものでございます。
ただ、同法は、書籍等の盗難実態の多い一部の物品につきましては、法の規制の潜脱防止のため、対価の総額が一万円未満の取引であっても本人確認を行わなければならないこととしているところでございます。
本法案におきましては、一定の金額未満の取引についてその相手方に係る本人確認義務を免除することとすると法の規制を潜脱されるおそれがありますので、取引額による本人確認義務の免除の規定は設けなかったものであります。
一方、本法案におきましては、買受業者の負担を軽減するため、過去に買受けを行った際に本人確認を実施している相手方であって、その方の銀行口座への振り込みによって代金を支払う場合、これにつきましては、取引の相手方に係る本人確認を重ねてすることは不要としているところでございます。
今後、更なる負担軽減措置につきましては、事業者の皆様の御意見も伺いながら、また実態を踏まえて検討してまいりたいと考えております。
○石原委員 残すところ三十秒になりましたので、これで質問を終えます。