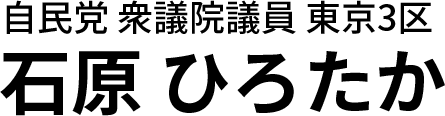憲法裁判所設置論と在外選挙権訴訟、靖国参拝問題
山本「何より、ご当選おめでとうございます。特別国会を終わられて、感想は如何ですか」
石原「42日間の特別国会を終えて、どうにか衆議院議員としての“てにをは”は身に着いた気がする。これからは、独自性を出せるように通常国会に備えたいと思う。衆議院では憲法改正を議論する特別委員会として「日本国憲法に関する調査特別委員会」が設置され、いよいよ本格的な憲法改正議論が進もうとしている。これまで以上に、このHPの場でもしっかり憲法改正の議論していくことが肝要だ」
山本「憲法改正に向けた国会の雰囲気というのはどのようなものでしょうか?」
石原「自民党は、立党50周年を迎え、記念式典が行われる11月22日に、党としての憲法改正案を提示する。また、今特別国会冒頭の代表質問に於いて、野党第1党民主党の前原誠司代表と鳩山由紀夫幹事長が憲法改正の必要性に言及した。正に、憲法改正を視野に今後、活発な議論がなされる土壌が整ったという雰囲気だ」
山本「なるほど。それでは、今後もこの対談の中で、国会での議論の状況も考慮しながら、しっかりと議論を深めていく必要がありそうですね」
憲法裁判所とは?
石原「さて、今回、山本君がテーマとして選んだのは、憲法裁判所の設置についてだ。まずは、憲法裁判所とはどのようなものか解説してほしい」
山本「はい。憲法裁判所と一口に言っても、いろいろなタイプのものが考えられます。ただ、一般に「もっぱら憲法事件の審査のために通常の司法・行政裁判所とは別に、特別に設けられる裁判所」と定義されています(大須賀明・栗城壽夫・樋口陽一・吉田善明編『憲法辞典』(三省堂、2001年)〔野中俊彦執筆〕)。通常の司法裁判所というのは、まずは当事者間に具体的なトラブル・事件があって、それを、法を適用して解決しようというものですよね。憲法裁判所は、基本的にこういった具体的トラブルを解決するわけではなく、あくまでも、問題とされる法律や処分が、憲法に適合しているのかどうかを審査し、判断する機関なのです」
石原「なるほど。具体的な喧騒から離れた高みの機関というわけだ(笑)。僕は、憲法裁判所といったとき、やはりドイツを思い浮かべる。ドイツの憲法裁判所は、たとえ具体的事件がなくとも、政府や国会議員(連邦議会議員の3分の1以上)の訴えによって、法律の憲法適合性を審査できる。例えば、日本では現状不可能とされているが、左党系の議員団が提訴して、自衛隊法の合憲性について憲法裁判所に判断させることも論理的にはできる」
山本「ええ。このようなケースを『抽象的規範統制』と呼んでいます。この場合、具体的事件がなくとも、提訴の要件さえ揃えば当該法律の合憲性について判断しなければならないということになりますから、少なくとも建前としては、軍事的・外交的な問題も判断する必要があります。実際、ドイツの憲法裁判所は、ドイツ軍のNATO域外派兵(1994年)や、徴兵制度の合憲性(2002年)について審査してきました」
石原「政府や、一定の議員の提訴よって憲法問題を審査できるとなると、当然、裁判所が政治問題に巻き込まれることになる。これは、首相の靖国参拝を違憲とする最近の高裁判決に鑑みても、議論する必要があるところだ」
山本「後で検討しましょう。ここでは、とにかく、憲法裁判所の性格を押さえることにします。この点、『司法権』と『違憲審査権』を、まずは概念上区別しておくことが有益だと思います」
石原「『司法権』というのは、平たく言えば、法を適用して具体的事件を解決する権限で、『違憲審査権』というのは、法律等の合憲性を審査する権限ということになる」
山本「そうですね。この区別を理解しておくと、なぜ憲法裁判所の導入に憲法改正が必要なのかがわかってくると思います。現行の日本国憲法の解釈上、『司法審査権』は『司法権』の中に包摂されていると考えられています。つまり、『司法審査権』は、具体的事件の解決に必要な限りで行使されなければならない、と。これを『具体的違憲審査制』とか、『付随的違憲審査制』と呼んだりしています。従って、具体的事件がなくとも審査を行えるような抽象的規範統制を認めるためには、然るべき憲法改正が必要であると考えられているのです」
石原「なるほど」
山本「ただ、憲法裁判所の権限は、抽象的規範統制に限られません。例えば、ドイツ型の憲法裁判所制度を採った場合、違憲審査権は憲法裁判所に独占されていますから、通常裁判所はこの権限を行使できないことになります。従って、通常の事件を審理しているなかで憲法問題に直面した場合、一旦、手続を中止して、憲法裁判所の判断を仰がなければなりません。憲法裁判所はこの場合にも権限を行使することになります。これを『具体的規範統制』と呼んでいます。その他にも憲法訴願という制度がありますが、今回は省略します」
在外選挙権訴訟と違憲審査 ― 憲法の裁判所の必要性?
石原「なるほど。憲法裁判所の内実がよくわかった。では、次に、今回のテーマとして『憲法裁判所』を選んだ理由を聞かせて欲しい」
山本「はい。第一に、つい先日(2005年9月14日)、在外選挙権訴訟で、日本の最高裁としては珍しく、かなり踏み込んだ違憲判決を出したということがあります。第二に、先程も触れられましたが、やはり首相の靖国神社参拝違憲判決がありますね(大阪高裁2005年9月30日判決)」
石原「では、まず第一点から議論しましょう。これは、海外に住む日本人の投票権を制限していた先般の公職選挙法の規定を違憲とする判決だった。小泉首相もこの最高裁判決に合わせて法整備を行うと宣言している」
山本「日本で史上7例目の法令違憲判決です」
石原「しかし、この判決がなぜ憲法裁判所設置論と関係しているのか?」
山本「憲法裁判所に関する議論の背景には、実は、これまでの日本の裁判所が違憲判断にきわめて消極であったという批判、反省があります」
石原「司法が過度に消極的になることは、『法の支配』という観点からも確かに問題だ。憲法に違反する状態があるのに、裁判所が積極的な違憲審査を控えるのであれば、憲法は単に絵に描いた餅に過ぎなきなる」
山本「ええ。実際、アメリカと比較して見ると、日本の違憲判決の少なさは際立っています。あまり知られていませんが、アメリカでは、裁判所の違憲審査権は憲法上規定されたものではなく、裁判所の判例で確立されたものに過ぎません(1803年Marbury v. Madison事件)。しかし、それにもかかわらず、1995年までに、アメリカの連邦最高裁は、連邦議会の制定した法律を134回も覆してきました。さらに、最近では、保守的な故レインキスト(W. Rehnquist)首席判事の下、こういった積極的な違憲審査の傾向は特に顕著であると指摘されています。2003年の資料によると、1995年以降、既に39以上の制定法を違憲として覆しているようです(Jed Handelsman Shugerman, A Six-Three Rule: Reviving Consensus and Deference on the Supreme Court, 37 GA. L. REV. 893, 893(2003))」
石原「歴史が違うとはいえ、日本の7回という数に比べると雲泥の差だ。日本の場合には、憲法81条で裁判所の違憲審査権をしっかり明記している。それにもかかわらず、この少なさとは」
山本「ええ。これをどう評価するかは、また別の問題ですが、確かにそういう事実はあるでしょう。最近の憲法裁判所設置論の背景には、憲法問題について専門に扱う憲法裁判所をつくり、こうした消極的な裁判所の態度を是正していこうという狙いがあります」
石原「なるほど」
山本「話を元に戻すと、先日の在外選挙権の違憲判決は、こうした議論の動向を踏まえて、最高裁自身が、自主的に違憲判断を活性化させていると読むこともできるのです。憲法裁判所のようなドラスティックな制度改革は、最高裁としても望むところではない、と」
石原「そういえば、在外選挙権訴訟後の新聞報道を見ても、最近、最高裁が、積極的な違憲判断を行うようになったとする指摘があった(小林武・読売新聞2005年9月15日)。このように見ると、憲法裁判所という抜本的な制度改革をしなくとも、最高裁の姿勢一つで、違憲審査権が活性化されると考えることもできる。そして、現在の最高裁がそういう方向性を打ち出していると考えることもできるわけだ」
山本「そうですね。そうすると、敢えて憲法裁判所を導入する必要性は、改めて議論されてよいようにも思われます」
司法消極主義? ― 運用レベルでの改善策
山本「加えて問題提起をしておくと、日本の最高裁は本当に消極的だったのでしょうか。実は、予てから、憲法裁判所設置論の根っこにある『司法消極主義』という認識そのものに異議が唱えられていました」
石原「それは?」
山本「確かに、最高裁が先日の在外選挙権訴訟以前に法令を違憲とした例として、刑法の尊属殺重罰規定を違憲としたもの(昭和48年)、薬事法の距離制限を違憲としたもの(昭和50年)、衆議院の定数不均衡を違憲としたもの(昭和51年と昭和60年の2回)、森林法の共有林分割制限規定を違憲としたもの(昭和62年)、郵便法の賠償責任制限規定を違憲としたもの(平成14年)が挙げられるに過ぎません。その意味で『消極主義』というのは妥当だと言えるでしょう。しかし、違憲判断には消極的であっても、憲法判断に消極的であったと言えるのでしょうか」
石原「なるほど。言われてみれば、事件の解決に必要がないのに、『念のため』といって、憲法判断に踏み込んだ朝日訴訟があった」
山本「そうです。朝日訴訟などは、途中で原告が死亡し、事件自体を判断する必要がなかったのに、敢えて生存権(25条)の性格について論じている。この点について、辻村みよ子教授は、『日本の最高裁判例では合憲判決は数多く存在するのであり、合憲判断積極主義で違憲判断消極主義であるといわざるをえない』と指摘しています(『比較憲法』(岩波書店、2003年)」
石原「合憲判決が多いということは、立法府や政治部門の判断にお墨付きを与えていることが多いということだ。それはある意味で、権力機関の決定を追認する迎合的な裁判所といえるかもしれない。論者が指摘する通り、日本の最高裁が、実は従来から、権力迎合的という意味で『司法積極主義』であったとすれば、さらに司法判断の積極性を増す憲法裁判所の導入は、一体何を意味するのか、よくわからなくなる」
山本「難しい問題ですね。そうなると、最高裁判事の任命手続など、もっと別の改革案を考えなければならないのではないか、という疑問が湧いてきます」
石原「積極的で、しかも『中立的』な違憲審査権を期待するには、任命システムの問題、裁判官の人事システムの問題など、もっと突っ込んで検討してみる必要がありそうだ。さらに、最高裁が抱える膨大な処理件数や、内閣法制局や議院法制局による法案の事前審査も検討しなければならない。今後、自民党や国会内でもこうした議論を提起してみたい」
靖国参拝と憲法裁判所
山本「こうみると、憲法裁判所設置を論ずる前に、手をつけることというのは、意外に多いように思えますね。ただ、今回、むしろ議論してみたいのは、靖国参拝との関連です。石原さんは、あの大阪高裁の違憲判決をどう読んでいますか?」
石原「僕は、基本的に信教の自由、政教分離の問題で大事なことは、国家が権力を傘に、国民に特定の宗教を強要したり、特定の宗教を弾圧するようなことを行わないことだと考えている。憲法解釈上、首相が個人的な参拝だと説明していても、公用車を使ったり、SPを同行したからといって、それはある意味、公的な参拝だと判断し、首相が靖国神社への信仰を国民に押し付けているといった解釈をするのは行き過ぎだと思う。」
山本「裁判官についてはどう思いますか?」
石原「大阪高裁の大谷正治裁判長がどの様な考え方の持ち主か、過去の判例でどの様な判断を下してきたか分からないので、コメントのしようがないが、個人的な感想はやはり、行き過ぎた判決だと思う」
山本「なるほど。実は、こうした感情というのは、違憲審査権の活性化を論ずる議論の対極にあると思います。例えば、週刊新潮10月13日号には「『靖国参拝』を違憲とした高裁裁判長の『陶酔判決』前科」(139頁から141頁)と題する裁判官バッシングがありますが、注目すべきでしょう」
石原「というと?」
山本「もし、週刊新潮の記事に納得し、同時に、違憲審査権の活性化を主張する場合、それはある種の自己矛盾を抱え込んでいるということになります。これは重要な論点です。先程も触れましたが、最高裁の『消極主義』の背景には、職業裁判官をキャリアシステムの中で育成する現行の人事システムの問題が指摘されています」
石原「つまり、没個性的で、体制迎合的な裁判官が、司法の消極性を再生産している、という批判だ」
山本「そうです。そうすると、司法の『積極性』を期待するならば、ある程度、個性的で体制迎合的ではない裁判官を受忍する必要もあるのではないでしょうか」
石原「いや、それは即断できない。『個性的』ということと、『非常識』ということとは話が違う。違憲審査権の積極化を説く見解は、あくまでも個性的で、かつ常識的な裁判官に権限を行使してもらいたいと思っているのではないか」
違憲審査と民主主義
山本「なるほど。ここでちょっと意地悪な質問をしたいと思います。石原さんにとっての『常識』とは何でしょうか?」
石原「それは、本当に意地悪な質問だ。全ての『常識』が不変的だとは思わないが、『人を殺してはいけない』とか『親を大切にしよう』とか不変的な常識もある。一方で、時代時代で『常識』といわれるものが変わることもあると思う。但し、『常識』とは、世の中を安定させる、秩序を守る、国益を守るための共通の意識だと思うから、その観点から、僕自身は、首相の靖国参拝への大阪高裁の判決は、行き過ぎだと考えている訳だ。もし、首相が近所の神社に参拝したら、それが憲法違反になるのだろうか?中国、韓国といった近隣諸国から批判され、世の中が安定しないじゃないかと言う人もいるかもしれないが、僕は靖国の問題を中国や韓国が非難するのは外交上の交渉カードに利用しようとか、国内の不満分子の目を日本に向かわせようとか、その程度のことであって、そのことに臆して、日本が卑屈になることの方が、日本人がプライドを失い、結果として国益に成らないし、国内が安定しないと思う」
山本「なるほど。ただ、仮に宗教的少数派を基準にして考えれば、あの判決はきわめて『常識的』だったかもしれませんね。これは、揚足を取っているわけではまったくありません。実は、裁判所による違憲審査権の行使というのは、民主主義、この場合の『民主主義』は『多数者支配的な民主主義(majoritarian democracy)』ということですが、それと緊張関係を持ちうる、ということを指摘したかったからです」
石原「これはあまり議論されていないが、確かに重要な論点だ。先程は、日本の最高裁は『体制迎合的』といったが、これは別の言い方をすれば、『民主主義的』といえるかもしれない。ある種のジレンマだ」
山本「その通りだと思います。憲法裁判所の導入というのは、実は、こうした違憲審査と民主主義の緊張関係を議論してから行う必要があると思うのです。先も触れましたが、ドイツの例を見る限り、憲法裁判所は、軍事・外交・治安に関する問題など、本来は政治家が、あるいは『民主主義』が決めるような政治的イシューについて判断せざるをないということになります。そして、少なくとも理論上は、こういった問題が、多数者の意図に反して、あるいは『反』民主主義的に、一部の裁判官の憲法解釈に基づいて判決される可能性があるというわけです。先の靖国参拝違憲判決への反応を見ていると、日本人にそういった深い覚悟ができているかどうかは疑問です。ある意味で、それは立憲主義的な覚悟だと思いますが…」
石原「確かに、微妙な価値対立を孕む憲法問題を、一部の裁判官が積極的に判断するということは、民主主義を苛立たせるものかもしれない」
山本「人種的少数派であった黒人の権利保障を実現した画期的判決とされるアメリカのブラウン判決(Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483(1954))も、実際には南部白人の凄まじい暴力を生みました。リトルロック事件やブルコナー事件です。前者は、クリントン前大統領の伝記にも登場しますが、アーカンソー州リトルロック市で1957年に起きた事件です。公立高校における白人・黒人の共学を命じた裁判所命令を、当時のフォーバス知事が州兵を動員して阻止しようとし、最終的にはアイゼンハワー大統領による連邦軍空挺団の派遣でようやく沈静化した、という事件です」
石原「まるで内戦だ」
山本「そうですね。後者、つまりブルコナー事件は、1963年にアラバマ州バーミンガムで起きた事件ですが、当時の公安委員長コナーが、非武装で、しかも非暴力的に行われていた公民権運動の参加者を(注、現在は一般に「市民権運動」と呼ぶ)、警察犬と消火ホースを用いて四散させた、という事件です」
石原「ブラウン判決には、マイナスのインパクトもあったというわけだ」
山本「裁判所が頑張ることはリスクも伴う。つまり、『影』の部分もあるというわけです(詳細は、MICHAEL J. KLARMAN, FROM JIM CROW TO CIVIL RIGHTS(2004))。裁判所が積極的な違憲審査権を行使して、少数派の権利を保障するということは、実は相当コストのかかることなのです」
石原「この点に配慮してか、ドイツの憲法裁判所でも、違憲判断は100件に1件、全体の約1%と少ない。しかも、やはり政治的配慮があると聞く」
山本「そうであるならば、なおさら、憲法裁判所設置は議論される必要があるのではないでしょうか」
まとめ
石原「今回の議論で、裁判所の違憲審査権というものが、実は、『憲法』と『民主主義』の微妙なバランスの上に成り立っていることがわかった。確かに、靖国参拝のような、微妙な憲法問題を、民主的に選挙されていない一部の裁判官が積極的に判断することそれ自体の問題が、いま問われるべきなのではないだろうか。僕としては、憲法問題は、まずは国民に選挙された政治家がしっかりと討議し、出来る限り違憲の疑いのある法律を立法しない、という決意が必要なのではないかと思う。裁判所の違憲審査は、あくまで補完的なセーフガードであって、憲法を保障する唯一の機関ではないと考える。求められるのは、憲法感覚のある政治家である」